 |
漬物・茨城県産・国産漬物・梅干し、たくわん、奈良漬け、浅漬けの茨城県漬物工業協同組合
|
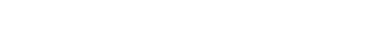 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本の食事の基本は一汁一菜で、米の御飯に味噌汁、漬物がつきます。
「今朝の漬物は美味かった。一日、一生懸命働けるよ」「昨日、畑でとれた茄子と胡瓜ですよ」奥さんと旦那さんの朝の会話です。
白い御飯に漬物、最高の食卓です。私たちは、春夏秋冬、季節にあった野菜を収穫して、それらをいろいろな方法で漬けて、食べてきました。
ここでは、漬物のお話をしますが、漬物を漬けるのに欠かせないものが塩です。
野菜や魚を保存するため、最初、海水を利用した時代もありますが、製塩の方法を古代人は考えました。
そして、山国の人たちにも、供給しました。
その塩によって味噌、醤油も作られるようになり、漬物は、ますます美味しくなりました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
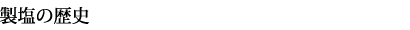 |
|
|
海水から塩をとる技術は、古い時代からかなり発達していました。
縄文時代の遺跡から製塩土器が出土しています。
まず、県内の塩作りの歴史を探ってみます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
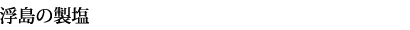 |
|
|
奈良時代に書かれた『常陸国風土記』信太郡の条に「乗浜の里の東に浮島の村あり。
(長さ二千歩(あし)、広さ四百歩なり)四面絶海(よもうみ)にして、山と野と交錯(まじ)り、戸(いえ)一十五烟(とうあまりいつつ)・・・居(す)める農民は塩を焼きて業(なりわい)と為す」とあります。
現在の稲敷市で、かつての桜川村浮島です。
農民は塩を焼いて、商売にしていました。 |
|
|
|
|
|
|
|
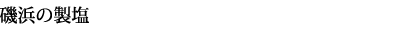 |
|
|
貞観13年(871)に書かれた『文徳実録』の斉衡3年(856)12月の条に「鹿島郡大洗磯前に神あり、新たに降る。
初め郡民海を煮て塩を作る者有り」とあり、鹿島灘の大洗の海岸に住む者は、海水を塩窯で煮て、塩を作るものが多かったというのです。
海水は清浄であるので、大洗の神とのつながりもありました。
塩を煮るのには黒松が燃料として重要でした。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
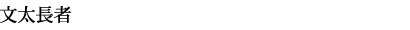 |
|
|
中世に書かれた『御伽草子』の中の「文正草子」は角折(鹿嶋市・旧大野村)が舞台になっています。
鹿島神宮の下働きをしていた、文太が塩焼きをして長者になる話です。
自給していた塩を各地に販売し富を得たのです。
塩釜神社には塩土翁がまつられ、ここから船に塩を積んで各地に送ったともいいます。 |
|
|
|
|
|
|
|
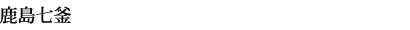 |
|
|
製塩業の発達には鉄釜が必要でした。
鹿島郡は砂鉄の産地で、今でも「鍛冶台、たたら跡、かじや町」の地名が残っています。
そして、鹿島郡には「鹿島七釜」がありました。
現在、地名になっています。
上釜(鉾田市・旧旭村)、別所釜・武与釜・高釜、京知釜・堺釜(鉾田市・旧大洋村)、武井釜(鹿嶋市・旧大野村)がそれです。
「住民が生活に困窮したとき、夢に、鹿島様が現れ、海に面して製塩に適しているので、塩を焚いて立てるのがよい」との伝承もあります。
治承4年(1181)に源頼朝が塩浜を鹿島神宮領に寄進しましたが、後になって、領地争いのもとになりました。塩浜でとる塩の所有争いのようです。 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
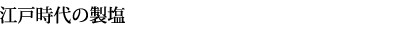 |
|
|
江戸時代には、『茨城の科学史』(P137「常陸の製塩」)によると、日立市(旧金沢村)の佐藤与市右衛門が浜塩田法を、正徳年間(1711〜16)に採用しました。
ひたちなか市(旧前浜村)でも文化年間(1804〜18)に豊後国から技術者を迎え、新しい製塩を行いました。
海水を塩田にまき、乾いた砂を笊(ざる)に入れ、再び、海水をかけて濃い塩水にして煮ます。
瀬戸内海は波が穏やかなので「入浜式製塩法」ですが、鹿島灘は波が荒く、「揚げ浜式製塩法」を導入しました。
塩場を波打際から30間離れたところに作り、海水を汲み上げました。
常陸国の塩は暮れ塩といわれ流通しました。
日立の塩は常陸太田、大子へ運ばれ、鹿島の塩は行方へ出荷されていました。
この塩を運んだ道を塩街道といい、各地に残っています。
塩町、塩横町など塩の取引が行われました。 |
|
|
|
|
|
|
|
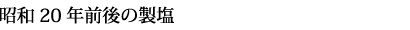 |
|
|
終戦前後、塩が不足し、漬物を漬けられなくなりました。
昭和17年に食塩は通帳配給制となり、味噌、醤油も配給制になりました。
この配給も昭和20年には配給停止になり、漬物が食べられなくなりました。
海水をビンにつめて持ち帰ることもありました。
『大野村史』(現鹿嶋市)によると、村民は海水を汲んでトタン釜で製塩し、かなりの収入を得たが、昭和23年の専売法制定などにより、製塩は中止されました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2012 IBARAKI TSUKEMONO KOGYO KUMIAI. All rights reserved. |
|
|
|